Seminar on Mechanical Engineering 1
機械機能工学科のカリキュラムは、エネルギー、物質、情報の3分野を柱として配置され、工学に対する興味が持て、将来展望に対する様々な進路に応じて履修計画ができるようになっていますが,機械工学の裾野は広く、通常の講義や実験・実習の中では接することのできない興味深い部分が多くあります。「創成ゼミナール」では、例えば、学科の教員が通常の授業の中では取り上げられないような事例・内容を取り上げ、機械工学をより広い視野から眺め、体験し、お互いに相互のコミュニケーションの中で、さらに機械工学を興味深いものにしようと試みるものです。講義のテーマや実施方法は、時代の変革とともにその一部が変更される場合もあります。学生はこれらのテーマから2つを選択し,それぞれ7回の講義で調査結果等の発表を行うことになる.
「創成ゼミナール」では、学科の教員が通常の授業の中では取り上げられないような事例・内容を取り上げ、機械工学をより広い視野から眺め、体験し、お互いに相互のコミュニケーションの中で、さらに機械工学を興味深いものにしようと試みることを目的とします。講義のテーマや実施方法は、時代の変革とともにその一部が変更される場合もあります。学生はこれらのテーマから2つを選択し,それぞれ7回の講義で調査結果等の発表を行うことになります.
- 学生各人が選択した分野に関する文献および情報等の検索と調査方法に習熟する.
- 調査結果から新たな問題を発見し,問題を文章としてまとめることができる.
- 調査結果および問題を文章としてまとめ,それらを総合的に工学的なプレゼンテーションができ,報告書としてまとめることができる.
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | 創成ゼミナール概要説明会 | 担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 2. | No.1 Design of flexible devices:G-PBL,担当:前田真吾 First half: 7 times Instructor: Shingo Maeda Outline:Recently, soft actuators, robots and devices are promising in various fields. So, in this class, mixed groups from KMUTT and SIT will present the original concept of flexible devices or robots. The following points should be considered. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 3. | No.2 ロボティクス,メカトロニクスの現状と将来応用(前半),担当:松日楽信人 今後の少子高齢社会に対してロボティクスやメカトロニクスなどを応用した製品が増えてくることが予想される.本ゼミではそのような分野に対してロボティクスやメカトロニクスの現状を調査し今後の方向性を議論する.そして実際の展示会に参加することで,それらが妥当であったかを確認する.また,調査結果に基づき,各グループでロボティクスやメカトロニクスを利用して,どんな機器をこれから開発すべきかを提案する.現在の課題を学ぶとともに展示会への参加の仕方や展示側の生の声に触れることで技術のあり方を学ぶ.さらに,地域の課題を解決するために提案内容のニーズ調査や発表の際に地域の方々との議論を行う. ※福祉機器展での見学・調査を検討しています. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 4. | No.3 ラジオメータの回転機構の考察と試作実験(前半),担当:小野直樹 簡単な翼構造を持ち,真空ガラス球内に支持され光を当てると回転するラジオメータを取り上げ,その運動機構を熱流体工学的に検討する.また回転翼部分を班毎に自作し,真空容器内で実際に回転させて回転速度を競い,同時に高速回転させるためのアイディアや課題点を議論する.また本年度は容器内の圧力値と回転力(回転数)との関係も計測し考察する. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 5. | No.4 太陽熱利用と冷やす技術を考える(前半),担当:田中耕太郎 太陽熱利用による低温度域エネルギーの貯蔵,変換技術,ものを冷やす技術の調査を行う.各種方法の原理と特徴を学ぶ.また,実際に実験が可能なものを選択し,具体的な作動を確認する.その他,将来の省エネルギー社会に必要となる,リサイクルと設計へのフィードバック,LCA(ライフサイクルアセスメント)を学ぶ. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 6. | No.5 交通システムの高度化にむけて(前半),担当:山本創太 現在,道路交通システムは通信・情報技術を積極的に導入し,車車間通信,ナビゲーションシステムの高度化,自動車の知能化による安全性向上を目指す動きがある.しかし,道路交通は,車,歩行者,自転車などの混合交通であること,相対距離に対して移動速度が高く回避がとりにくいこと,交通密度が高いことなど課題が多い. 本ゼミナールでは,交通システムの高度化における課題とその解決に向けての指針を検討する.まず,道路交通システムの高度化に対して現在までに提案されている将来像,次世代技術とそこに存在する課題について討論しながら学ぶ.次に,水上交通における管制を学ぶ実習を実施し,水上交通のルールとその運用,および用いられている交通管制技術について知るとともに,交通管制のあるべき姿,必要なことが何であるかを討論する.水上交通システムの実習は,東京海洋大学 汐路丸にて実施の予定である.東京海洋大学から特別講師として庄司るり先生をお招きする. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| 7. | No.6 構造物の動的設計(楽器の設計,製作)(前半),担当:細矢直基 構造物の振動特性,及び音響特性を考慮した動的設計について,鉄琴の設計,製作を通して学ぶことを目的とする.まず,はじめに振動解析に必要なデータ処理方法の一つである高速フーリエ変換を学び,これを実現するためにMATLABによるプログラミングを習得する.次に,はりの厳密解を導出し,構造物の固有値,および固有ベクトルを理解する.最後に,製作した鉄琴の振動測定,音響測定,有限要素法解析(NASTRAN)を行うことで,所望の振動特性,及び音響特性の鉄琴が製作できたことを示す. |
担当教員の指導に従って課題に取り組むこと. | 190minutes |
| Total. | - | - | 1330minutes |
| プレゼンテーション | レポート | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 16% | 17% | 33% |
| 2. | 16% | 17% | 33% |
| 3. | 17% | 17% | 34% |
| Total. | 49% | 51% | - |
以下の番号は,授業計画の番号に対応します.No.1からNo.12番号のテーマによる評価方法は異なるが、各テーマは100点または100%(%は点に変換)で評価する.成績評価は、各自が選択した2テーマに関して,総合計/2の平均点から行い、60点以上を合格とする.
No.1. ライントレースロボット設計製作・プログラム開発(50%)プレゼンテーション(50%)で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.2. プレゼンテーション内容(50%),レポート内容(50%)で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.3. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.4. 発表内容50%,レポート内容50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.5. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.6. プレゼンテーション(内容,発表資料の完成度を含む)50%,提出レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
14. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.1. ライントレースロボット設計製作・プログラム開発(50%)プレゼンテーション(50%)で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.2. プレゼンテーション内容(50%),レポート内容(50%)で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.3. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.4. 発表内容50%,レポート内容50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.5. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
No.6. プレゼンテーション(内容,発表資料の完成度を含む)50%,提出レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
14. プレゼンテーション50%,レポート50%で評価し,総点100点で60点以上を合格とする.
- 授業のある金曜日,授業の昼休みに対応します.これ以外の時間では,研究室に在室中は,可能な限り対応します.(青木,松日楽,田中,高崎,小野,橋村,山本,長澤,細矢,斎藤,前田,廣瀬)
- Course that cultivates an ability for utilizing knowledge
- Course that cultivates a basic interpersonal skills
- Course that cultivates a basic self-management skills
- Course that cultivates a basic problem-solving skills
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicatable |
|---|---|
| N/A | 該当しない |



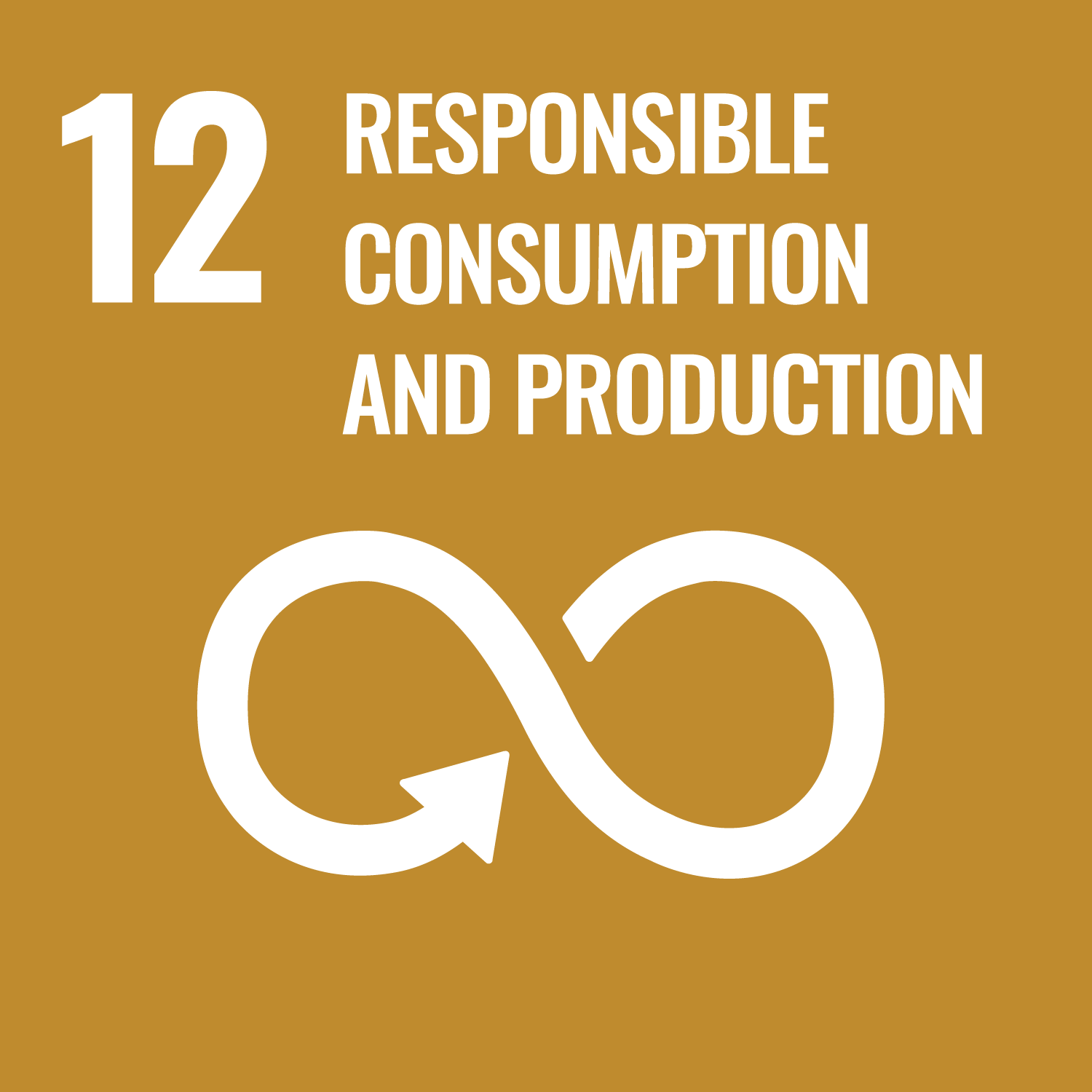
- 4.QUALITY EDUCATION
- 7.AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
- 9.INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
- 12.RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION
Last modified : Sun Sep 13 04:03:06 JST 2020
