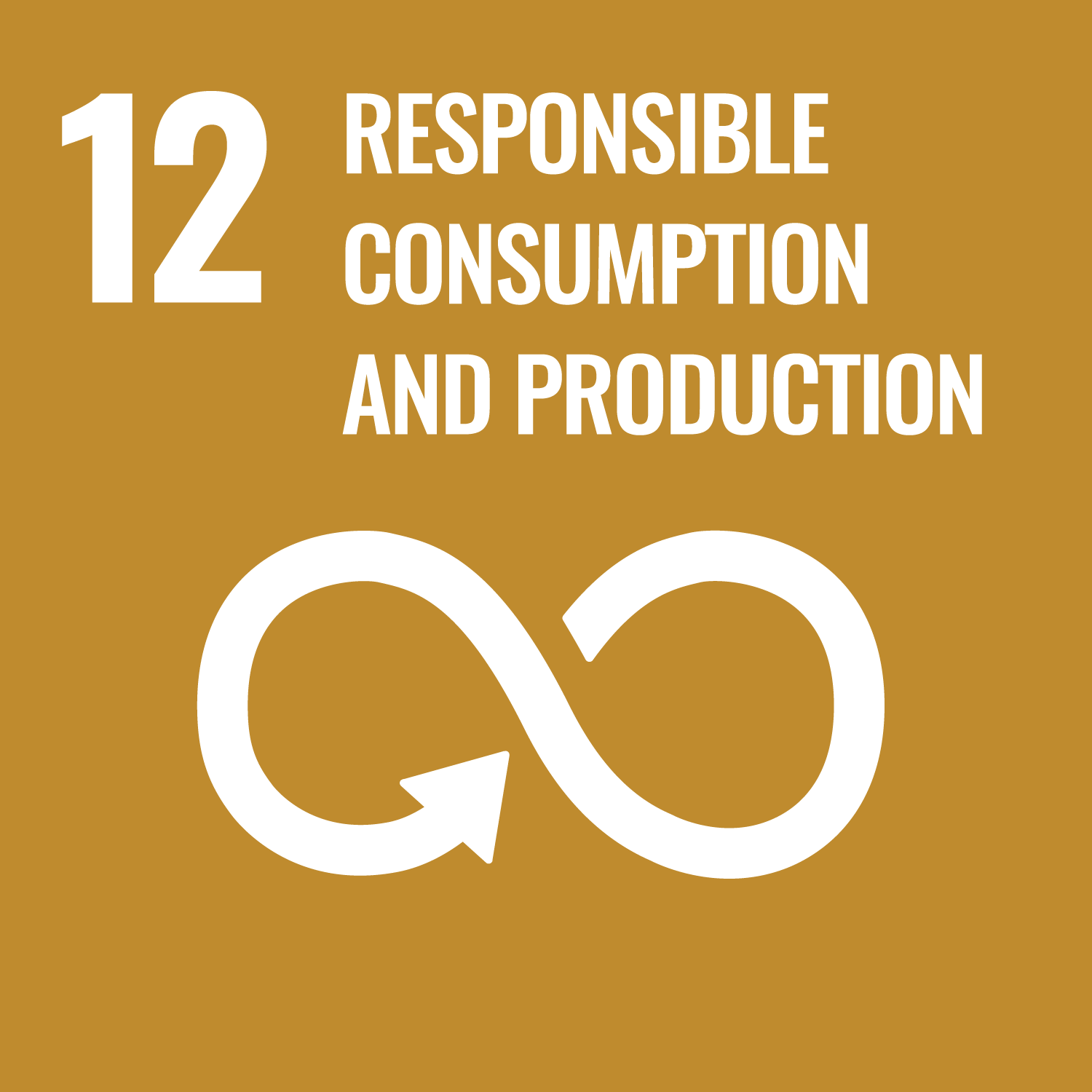最近の加工技術の発達は,材料・工具・機械の進歩と制御技術の向上などと相まってめざましい物がある.その動向として従来の加工技術の改良といった面にはとらわれず,新しい発想が取り入れられているのが特徴である.本講義では加工技術の中から塑性加工を取り上げ,その各種加工方法の特徴を解説し,金属材料特性などとの相関について学習する.
| 達成目標 | 学修・教育到達目標との対応 | |
|---|---|---|
| 1. | 機械を構成している要素部品の加工技術としての塑性加工に関して,各種加工方法の特徴を理解し,加工手段の選択ができる. |
D
|
| 2. | 塑性加工用金属材料の特徴と変形に伴う材料特性の変化の特徴を理解し,適切に材料と加工条件の選択ができる. |
D
|
| 3. | 塑性加工時に生じている応力とひずみの状況を理解し,その状況を塑性力学によって表現できる. |
D
|
| 授業計画 | 授業時間外課題(予習および復習を含む) | 必要学習時間 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 塑性加工の特徴 ・各種加工法との比較 |
シラバスの確認. | 60分 |
| 「加工学」,「マテリアルサイエンス」の復習 | 130分 | ||
| 2. | 塑性力学の基礎(1) ・真応力と真ひずみ ・多軸応力状態とモール円 |
材料力学の復習. | 120分 |
| 教科書1.4まで目を通す. | 70分 | ||
| 3. | 塑性力学の基礎(2) ・降伏条件 ・多軸の応力とひずみ状態 |
前回の復習. | 120分 |
| 教科書1.6まで目を通す. | 70分 | ||
| 4. | 塑性力学の基礎(3) ・塑性加工の初等解法 |
前回の復習. | 120分 |
| 教科書1.7まで目を通す. | 90分 | ||
| 5. | 塑性加工用材料の特徴 ・塑性変形の機構と材料の変形挙動 ・変形温度と塑性の相関 ・塑性変形と材料特性 |
「加工学」,「マテリアルサイエンス」の復習 | 120分 |
| 教科書第2章に目を通す. | 70分 | ||
| 6. | 塑性加工用材料の特徴 ・各種金属材料の特徴 塑性加工用工具材料の特徴 ・各種工具用金属材料の種類と特徴 |
前回の復習. | 120分 |
| 教科書第2章に目を通す. | 70分 | ||
| 7. | 中間試験および解答解説と講評 | 講義第1〜5回の内容の復習. | 190分 |
| 8. | 圧延加工 ・板圧延 ・圧延機の種類 ・型圧延と管圧延 |
教科書第3章に目を通す. | 190分 |
| 9. | 押出し加工 ・分類と特徴 ・押出し加工の理論式 ・押出し用機械および金型 引抜き加工 ・分類と特徴 ・引抜き荷重の理論式 ・引抜き用金型・機械および潤滑 |
教科書第4章に目を通す. | 100分 |
| 教科書第5章に目を通す. | 90分 | ||
| 10. | せん断加工 ・分類と特徴 ・荷重状態とせん断面形状 ・プレス機械と金型 ・ファインブランキング |
教科書第6章に目を通す. | 190分 |
| 11. | 曲げ加工 ・分類と特徴 ・板の直線曲げ ・スプリングバック ・管の曲げ |
教科書第7章に目を通す. | 190分 |
| 12. | 深絞り加工 ・板の変形 ・加工限界と加工条件 ・再絞り加工と特殊加工 |
教科書第8章に目を通す. | 190分 |
| 13. | 鍛造加工 ・分類と特徴 ・熱間鍛造と冷間鍛造 ・鍛造の加工因子 |
教科書第9章に目を通す. | 190分 |
| 14. | 定期試験および解答解説と講評 | 講義第7〜14回の内容の復習. | 190分 |
| 合計 | - | - | 2680分 |
| 中間試験 | 期末試験 | 出席演習 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10% | 30% | 10% | 50% |
| 2. | 10% | 0% | 5% | 15% |
| 3. | 15% | 10% | 10% | 35% |
| 合計 | 35% | 40% | 25% | - |
【評価方法】講義中に演習やレポート等を課すが,成績評価はそれらの結果(25%)と中間試験(35%)と期末試験(40%)の結果を総合して評点(100点満点)を計算する.この評点が60点以上となった場合に合格とする.
【評価基準】塑性力学の基礎を理解し,基本的な塑性加工の課題に対して,基礎を適用して材料に応じた加工方法の提案ができるレベルを合格とする.
【評価基準】塑性力学の基礎を理解し,基本的な塑性加工の課題に対して,基礎を適用して材料に応じた加工方法の提案ができるレベルを合格とする.
教科書:「塑性加工入門」日本塑性加工学会 編,コロナ社
参考書:「塑性加工の基礎」村川・中村・青木・吉田 共著,産業図書
参考書:「基礎塑性加工学」川並・関口・斉藤・廣井 編著,森北出版
参考書:「塑性加工(改訂版)」鈴木弘 編,裳華房
参考書:「金属塑性加工学」加藤健三著,丸善 他
参考書:「塑性加工の基礎」村川・中村・青木・吉田 共著,産業図書
参考書:「基礎塑性加工学」川並・関口・斉藤・廣井 編著,森北出版
参考書:「塑性加工(改訂版)」鈴木弘 編,裳華房
参考書:「金属塑性加工学」加藤健三著,丸善 他
最終更新 : Sat Mar 21 14:20:09 JST 2020