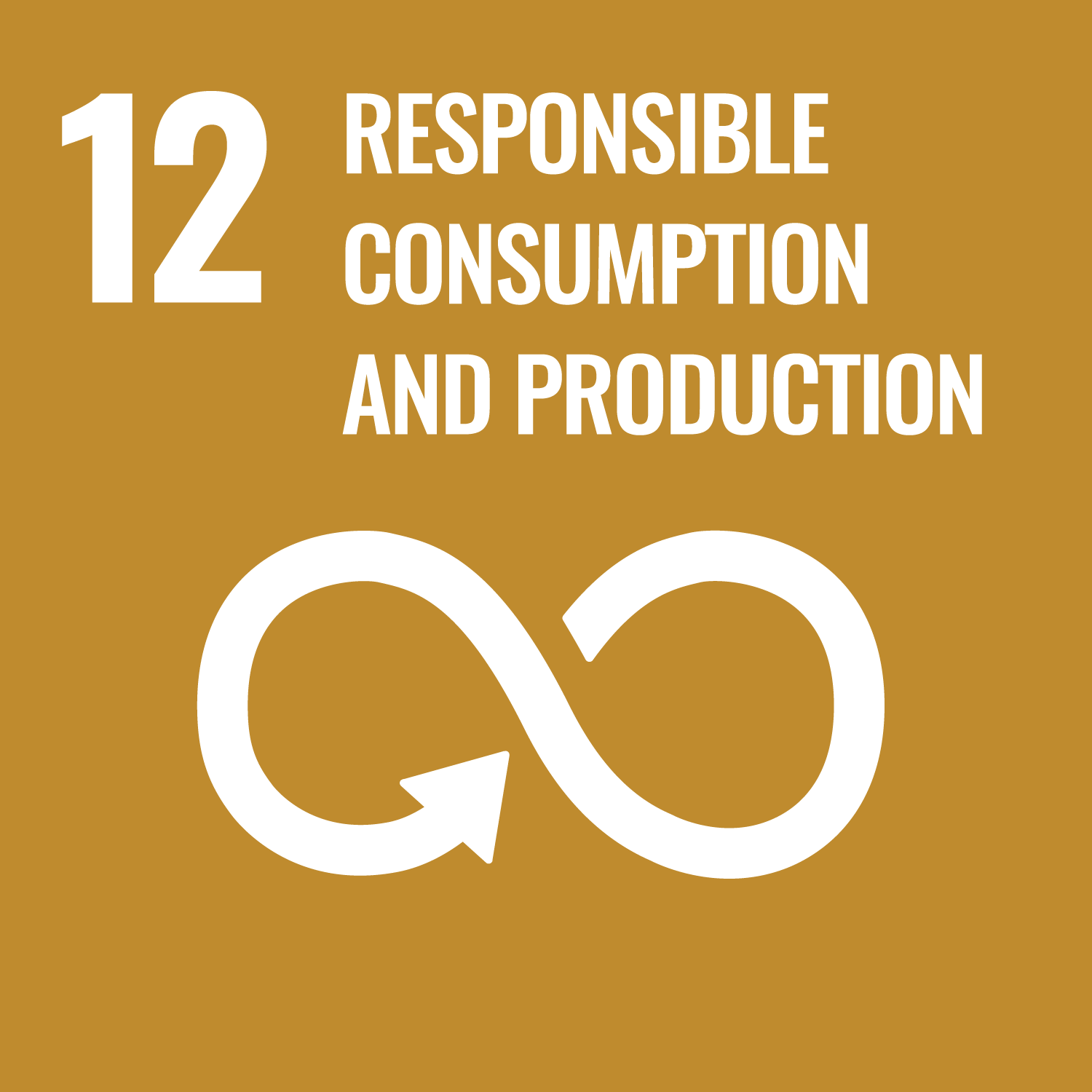建築・都市・環境の基盤となる最先端の構造システムとして、建築構造システム(石川)研究室では,地震国である日本において超高層建築を実現するために必要な次世代レジリエントRC構造として高強度SFRC構造の実現や高強度CFT構造に関する研究活動を行っています。加えて、資源循環型社会を実現する木制震構造システムの研究開発を進めている。これらの最先端(Edge)研究に取組むことにより、次代を担う人材を輩出することを目指している。
- 現在の日本及び世界が解決すべき建築構造に関する課題を把握し,その現状を理解すると共に新たな研究課題を提案することが出来る。
- 鋼繊維(ベルギー)やLVL・CLT(ニュージーランド)で実用化されている最先端材料の特性を理解し,その活用方法を提案することが出来る。
- 建築構造に関する最先端の研究課題に関する実験研究および解析的研究の研究計画の立案及び研究の遂行が出来る。
- 国内外の学会において,論文を投稿し発表することが出来る。
- 企業と連動した共同研究を遂行することにより,より高い社会人基礎力の向上が出来る。
1.高強度SFRC構造の実用化を目指した研究活動の実施
a)高強度SFRC曲げ特性を解明する
b)高強度SFRC柱に関する実験的研究によりを解明する
c)高強度SFRC有効強度係数を解明する
d)高強度SFRC 柱に関するFEM解析を用いた解析的研究によりを解明する
2.RC柱梁接合部の構造性能を解明する。
a)十字形・ト形接合部に関する接合部降伏破壊に関する実験的研究によりを解明する
b)プレキャスト柱梁接合部の構造特性を解明する
3.木制震構造の構造特性を解明する
4.Digital Image Correlation による非接触型計測システムの実用化研究の実施
5.超高層RC・CFT造建物のデータ分析により技術的動向を探究し,将来予測の立案
a)高強度SFRC曲げ特性を解明する
b)高強度SFRC柱に関する実験的研究によりを解明する
c)高強度SFRC有効強度係数を解明する
d)高強度SFRC 柱に関するFEM解析を用いた解析的研究によりを解明する
2.RC柱梁接合部の構造性能を解明する。
a)十字形・ト形接合部に関する接合部降伏破壊に関する実験的研究によりを解明する
b)プレキャスト柱梁接合部の構造特性を解明する
3.木制震構造の構造特性を解明する
4.Digital Image Correlation による非接触型計測システムの実用化研究の実施
5.超高層RC・CFT造建物のデータ分析により技術的動向を探究し,将来予測の立案
1.各種研究活動およびゼミにおけるレポート等の研究実績 50%
2.各種研究活動およびゼミにおける積極性 30%
3.コミュニケーション力および研究成果に関するプレゼンテーション能力 20%
2.各種研究活動およびゼミにおける積極性 30%
3.コミュニケーション力および研究成果に関するプレゼンテーション能力 20%
1.各研究課題に関連する論文や資料
2. N.J.N. Priestley: Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings
3. Jack Moehle:Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings
4. 青山博之:鉄筋コンクリート建物の終局強度型耐震設計法
5.日本建築学会:鉄筋コンクリート造建物の保有水平耐力計算規準・同解説
2. N.J.N. Priestley: Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings
3. Jack Moehle:Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings
4. 青山博之:鉄筋コンクリート建物の終局強度型耐震設計法
5.日本建築学会:鉄筋コンクリート造建物の保有水平耐力計算規準・同解説
| 実務経験 | 具体的内容 |
|---|---|
| 該当する | 大手ゼネコン技術研究所にて研究員20年,設計部構造設計者2年,現場関係部署経験1年を有すると共に建築の都市再開発計画から,設計施工に至る一連の仕事を経験した教員によって、建築構造力学の基礎に関する講義を行う。また、教員は,1級建築士の資格を有すると共に最先端の建築構造技術に関する研究開発者としての経験を有しており,学生に対して,実社会と連動する実務経験に基づく講義を実施することが可能である。 |
最終更新 : Sat Mar 27 04:04:58 JST 2021