Seminars on Civil Engineering
学生個人が自ら意見を持ち表現するとともに、学生同士で議論をすることで、プレゼンテーションやディスカッションなどのコミュニケーション能力を身につける。
学生を16名程度のグループ7班に分けて、2名の教員が隔週で担当する。内容は議論できるものならびに社会現場の見学・視察などを適宜取り入れることもある。
以下にいくつかの班(各教員)の講義内容を例として示す。
・現場見学会を2回実施(例:JR東日本品川新駅,足立区竹ノ塚連立,東横線地下化工事,京急線蒲田連立など)し、見学前に各事業担当者へのKey Question作成のためのグループディスカッションとプレゼン、見学会での意見交換会、見学会後に報告書の作成を実施する。(岩倉)
・講義の前半は、各学生による話題提供を行い、各話題に関して全員で討議を行う。話題提供内容は時事問題や土木に関連する問題から学生自ら提案する。後半は現場見学会を実施し、得られた知見や意義について議論する。(紺野)
・教員が地盤工学に関する話題提供を行い、その話題に関するレポート作成を行う。各学生が土木工学に関する話題の提供を行い、各話題に関して討議を行う。提案した話題に関してレポート作成を行う。(並河)
・課題図書について要旨をまとめて発表し、内容に関して全員で討議を行う。また、首都圏の洪水防護施設について事前調査を行うとともに見学会を行い、見学を通じて学んだことについてレポート作成を行う。(平林)
・海外の都市計画における先進事例をレビューし、その特徴や構造を地図上に整理する。その後、事例を通じて得た知識やアイディアを、日本のまちづくりへどう適用できるかについて、豊洲等の大学周辺地域を対象にして考え、計画図の作成・議論を行う。(大山)
・東日本大震災などの近年の自然災害の発生後、外国人の退避や防災対策に関する問題が生じました。本ゼミでは、安全かつ多様な社会を実現するため、在留外国人と外国人観光客のための防災対策に関する現状と課題を調べ、社会の多様化に興味を深める。(マイケル)
・講義の前半は、RESASや各種移動に関する統計データを活用して地域の抱える課題を把握する。後半は、国内外におけるスマートモビリティの事例を分析し、移動に関わる課題を解決する地域交通・観光方策等を討議する。(楽)
学生を16名程度のグループ7班に分けて、2名の教員が隔週で担当する。内容は議論できるものならびに社会現場の見学・視察などを適宜取り入れることもある。
以下にいくつかの班(各教員)の講義内容を例として示す。
・現場見学会を2回実施(例:JR東日本品川新駅,足立区竹ノ塚連立,東横線地下化工事,京急線蒲田連立など)し、見学前に各事業担当者へのKey Question作成のためのグループディスカッションとプレゼン、見学会での意見交換会、見学会後に報告書の作成を実施する。(岩倉)
・講義の前半は、各学生による話題提供を行い、各話題に関して全員で討議を行う。話題提供内容は時事問題や土木に関連する問題から学生自ら提案する。後半は現場見学会を実施し、得られた知見や意義について議論する。(紺野)
・教員が地盤工学に関する話題提供を行い、その話題に関するレポート作成を行う。各学生が土木工学に関する話題の提供を行い、各話題に関して討議を行う。提案した話題に関してレポート作成を行う。(並河)
・課題図書について要旨をまとめて発表し、内容に関して全員で討議を行う。また、首都圏の洪水防護施設について事前調査を行うとともに見学会を行い、見学を通じて学んだことについてレポート作成を行う。(平林)
・海外の都市計画における先進事例をレビューし、その特徴や構造を地図上に整理する。その後、事例を通じて得た知識やアイディアを、日本のまちづくりへどう適用できるかについて、豊洲等の大学周辺地域を対象にして考え、計画図の作成・議論を行う。(大山)
・東日本大震災などの近年の自然災害の発生後、外国人の退避や防災対策に関する問題が生じました。本ゼミでは、安全かつ多様な社会を実現するため、在留外国人と外国人観光客のための防災対策に関する現状と課題を調べ、社会の多様化に興味を深める。(マイケル)
・講義の前半は、RESASや各種移動に関する統計データを活用して地域の抱える課題を把握する。後半は、国内外におけるスマートモビリティの事例を分析し、移動に関わる課題を解決する地域交通・観光方策等を討議する。(楽)
- 様々な話題について教員や学生同士でコミュニケーションを深めることで、自分の考えをまとめ、表現することができる。
- 様々な話題について議論し、多方面に物事を考えることができる。
- 論理的にディスカッションすることができる。
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | ゼミナール(第1回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 2. | ゼミナール(第1回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 3. | ゼミナール(第2回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 4. | ゼミナール(第2回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 5. | ゼミナール(第3回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 6. | ゼミナール(第3回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 7. | ゼミナール(第4回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 8. | ゼミナール(第4回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 9. | ゼミナール(第5回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 10. | ゼミナール(第5回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 11. | ゼミナール(第6回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 12. | ゼミナール(第6回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 13. | ゼミナール(第7回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| 14. | ゼミナール(第7回) | 配布された関連文献や資料を熟読すること | 60minutes |
| Total. | - | - | 840minutes |
| 発表1(レポートなどを含む) | 発表2(レポートなどを含む) | 最終レポート | Total. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10% | 10% | 15% | 35% |
| 2. | 10% | 10% | 5% | 25% |
| 3. | 20% | 20% | 40% | |
| Total. | 40% | 40% | 20% | - |
発表(レポートなどを含む)を80%、最終レポートを20%として評価する。60点以上で合格とする。なお、現場見学でのレポートや議論への積極性は発表に取り込む形で採点する。
*各教員の担当ごとに学生とテーマを決定し、学生は調査した結果を発表する。また、それについて議論を加えることが望ましい。現場視察等においては、各回終了後にレポートの提出を実施する。
*最終レポートは、「半年間の講義を通じて、土木工学を学び、社会に貢献するために今後取り組んでいくこと」についてまとめることとする。
*各教員の担当ごとに学生とテーマを決定し、学生は調査した結果を発表する。また、それについて議論を加えることが望ましい。現場視察等においては、各回終了後にレポートの提出を実施する。
*最終レポートは、「半年間の講義を通じて、土木工学を学び、社会に貢献するために今後取り組んでいくこと」についてまとめることとする。
- Course that cultivates a basic interpersonal skills
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| N/A | 該当しない |


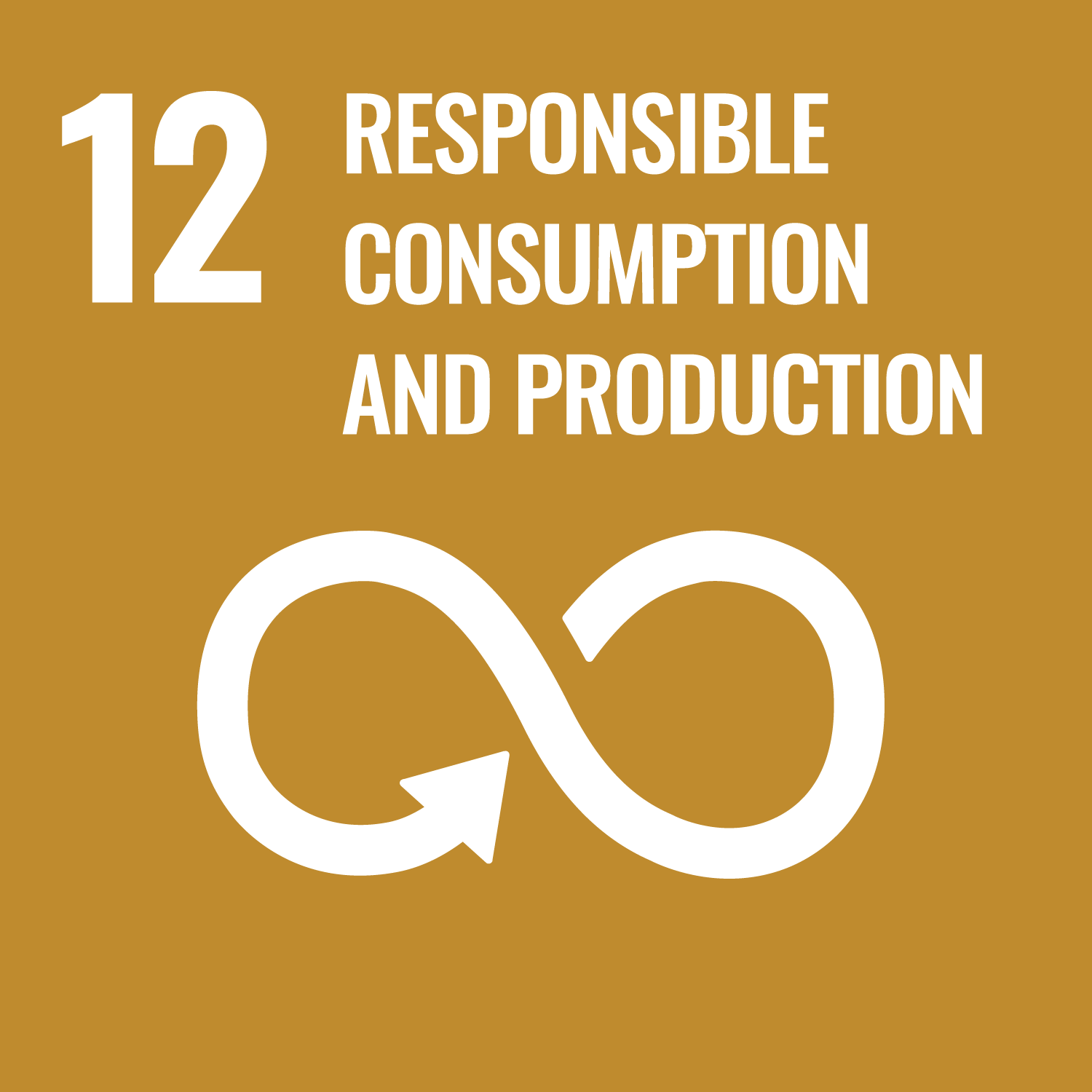

- 6.CLEAN WATER AND SANITATION
- 11.SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
- 12.RESPONSIBLE CONSUMPTION & PRODUCTION
- 13.CLIMATE ACTION
Last modified : Mon May 23 04:33:59 JST 2022

